
令和元年最初の年も暮れる、ということで鏡餅を作ってみることにした。数年ぶりだ。
前回は餅を乾燥させる時間がないまま、撞いて間もない餅をドッキングさせてしまった。そのせいで松の内が終わる頃にはカビだらけになり、年神様を喜ばせるのではなく部屋中のカビ菌を喜ばせるだけに終わってしまった。なんて博愛精神の持ち主なんだ、俺。
今年はその教訓を踏まえ、1日以上餅を乾燥させてみた。もうカビだらけの鏡餅はこりごりだ。
2019年はちょうど日程が良かった。27日が金曜日で仕事納めだったので、帰省まで少し時間が稼げたからだ。お陰で冬休みに入ってからでも、ゆっくり餅を準備する時間ができた。
ホームベーカリーでもち米を撞く。2合。
水ともち米を入れて、30分ほど蒸らし時間。その後の工程がちょっとおもしろく、ブザーが鳴るのでそれを合図にホームベーカリーの蓋を開く。その青空開放の状態で、餅つきが行われる。密閉空間でイヤラしく発酵と焼成が行われるパンとは大違いだ。
餅が自重で潰れてしまうのは避けたい。そんなわけで、つき上がったお餅は大小2つのお椀に一旦入れて、丸いシルエットになるようにしてみた。
大きい方はラーメンとかに使う丼、小さい方はお味噌汁を入れるお椀。
これで冷え固まったところで、オーブンで使う網の上に移し、360度から乾燥させること1日半。もっと乾燥させたかったけど、ここまでで時間切れ。
お椀に餅を入れて固める、というのはナイスアイディアだった。餅が潰れることなく、立体感ある形をキープした。しかし誤算だったのが餅の底で、ここまでは整形していなかったので形がいびつになってしまった。お陰で上の段のお餅が、若干バランス悪い。
お餅の上には橙(だいだい)を乗せるのだろうけど、そんなものは家になかったしサイズがあわない。なので、ちょうど手元にあった岡山みやげ、マスカットチョコレートの個包装のやつを1個ちょこんと乗っけてみた。
そして両脇には、狛犬よろしく新潟県・松之山温泉の名物「鳥こけし」を2羽配置。
床の間なんてものは存在しないマンション住まいなので、テレビのすぐ下で我が家を見守っていただくことにした。
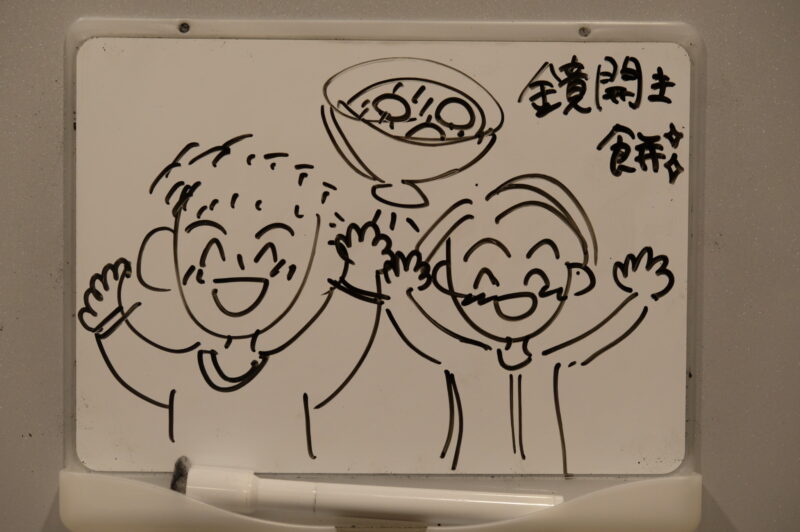
令和2年、2020年。あけましておめでとうございます。
というわけで、鏡開き当日。
夕食後のお夜食として、振る舞うことにした。さすがに朝、家を出る前にガッツンガッツンと餅を叩き割ってから調理するほどの時間的な余裕はない。

正月を乗り越え、制作から2週間近くが経った鏡餅。
さすがに表面にひび割れが出来ている。
さて、カビはどうだろうか。
もしカビていたら、ということで代打用の餅は用意してある。鏡餅をついた同じ日に「せっかくホームベーカリーを引っ張り出したんだから」ということでもう一回餅つきをし、それを冷凍庫で保存しておいたからだ。
それだけ、以前かびだらけのお餅を見たときのショックは忘れられないということだ。

鏡餅、表面はカビていないようだ。でも問題は裏側。
・・・恐る恐るひっくり返してみる。
まあ、一応カビは出ているけど、これならなんとかなりそうなレベル。
餅の底がなめらかではなく、凸凹が出来てしまったぶん乾燥が進み、カビにくくなったのかもしれない。

さて、叩き割るぞ。
いや、縁起物なのに「叩き割る」だなんて表現が物騒だ。「鏡開きをするぞ」と言い換えないと。
鈍器をいくつか用意してみる。最初、工具箱からスパナとモンキーレンチを持ってきたのだが、「そういえばキャンプ用にペグ打ちトンカチを昨年買ったっけ」と思いだした。
ペグ打ちトンカチを消毒し、いざ鏡割り。
ドスン、ドスン。
思ったより硬い。いや、全然硬い。振動がそのまま床に伝わる。餅はあくまでもトンカチの衝撃をまな板、机、そして床に伝達しているだけかのようだ。
何度かやっているうちに、さすがに不安になってきた。下の階の人から、「殺人事件か何かが行われているんじゃないか」と通報されるんじゃないかと。
上下左右の防音がけっこうしっかりした家に住んでいるけど、この不穏な衝撃音はさすがにごまかせない予感。
結局途中からは、割れ目が入ったところを軸に、手で餅を引きちぎるというやり方で鏡割りが行われた。「割っている」というより「引き裂いている」ので、ちょっと趣旨が違うけどまあいいや。

カビがついているところを包丁で削り落とし、おしるこにして食べる。
カビは全部取り除いたけれど、やっぱり餅には若干の埃っぽさ、というかカビ臭さは残っている。なので劇ウマとはいいきれないけれど、まあ風情ってやつですよ風情。
風情という言葉ですべてを片付けつつ、今年も正月気分はこれで終わり。さて次は節分気分で行こう。
(2020.01.11)

コメント