富士山は不思議な山だ。普段登山なんかに興味が全くない人であっても、いきなり「富士山に登りたい」って言いだす。これが「霊峰」のなせる技か!と思うが、だとしたら他にもたくさんある霊峰、恐山とか白山、立山にだって登りたいというはずだ。でもそういう話は全く聞いたことがない。
でもそれよりもなによりも、富士山のかっこよさは異常。360度どこのふもとから見ても、カッチョイイ。遠く離れた東京からでもそのかっこよさはひしひしと伝わってくる。古来から富士山が愛され、畏怖されてきたのは納得だ。富士山肴にしながら酒が何杯でも飲めるわ。
普通、山というのは登山口から谷沿いを歩いたり、せっかく稼いだ標高を無駄にするような下り坂があったり、尾根に出るために急なつづら折れの道があったりと起伏が激しい。それが当然。しかし、この日本一の山富士山は、あまりに美しいシルエット故、「アホみたいにひたすら登り続ける」だけの登山道なのだった。しかも、一般的に登山を開始する五合目(標高約2,400m)は森林限界であり、登っている間はひたすら砂利道。雷鳥さんがひょっこり顔を出したりするサプライズも、高山植物が可憐に咲き誇ることもない。
「富士山に一度も登らない馬鹿、二度登る馬鹿」とかいう格言がある。天下の名峰富士山に一回も登らないやつは馬鹿だ、と一刀両断だ。しかし、その後におまけがあって、「富士山のように登っていてつまらない山に二回も三回も登るのも、やっぱり馬鹿だ」というわけだ。なるほど言い得て妙だ。
おかでんは1995年に、パソコン通信Peopleネットのオフ会で既に一回登っており、その点では今回2度目なので馬鹿だ。でも、「馬鹿認定」されてしまうと、周囲から目を付けられてしまう。富士山に登った事がある人、ということで、「私も富士山に連れて行って欲しい」と依頼されるのだった。結局、1999年にも職場の同僚を連れて富士山に登り、見事「W馬鹿」の称号を手に入れた。
さて今回だが、ジーニアスからの「若いうちに富士山に登っておきたい」というリクエストに応える形で登山が実現した。ジーニアスはテニスを趣味としており、それなりに体は動かしてはいる。とはいえ、標高3,776mの富士登山は日頃の体力の有無とは別次元の気合いが必要であり、若干その点が心配。
おかでんとしては、登山初心者を高い山に連れて行くという登山の引率を初めてやるので、若干慎重。登山なんてのは、結局は自己責任の世界だけど、とはいえ何かトラブルが起きたら引率者の責任を問われてしまう。くれぐれも無理は禁物だ。進む勇気よりも退く勇気。
今回のプランとしては、夜9時過ぎから富士吉田口(河口湖側の登山口)から登り始め、山頂でご来光を眺め、持参した朝ご飯を山頂で食べてから下山、昼頃下山完了で夕方東京帰着・・・というプラン。
御殿場側の登山口二カ所は、距離が非常に長いのであまり人気はない。富士宮口は登山口がその他の登山口よりも一番標高が高いので、少しお得。そんな中で、ダントツの人気を誇るのが「吉田口」。吉田口の何が人気って、交通の便が良いのだった。河口湖まで中央高速でやってきて、そこから富士スカイラインに乗れば、ほとんど信号無しで五合目登山口まで到着できる利便性。観光バスで乗り付けてくる団体登山者は大抵ここを起点にするし、公共交通機関を使う人も、吉田口行きのバスに乗ってここにやってくる。とにかく人が多い登山口だ。


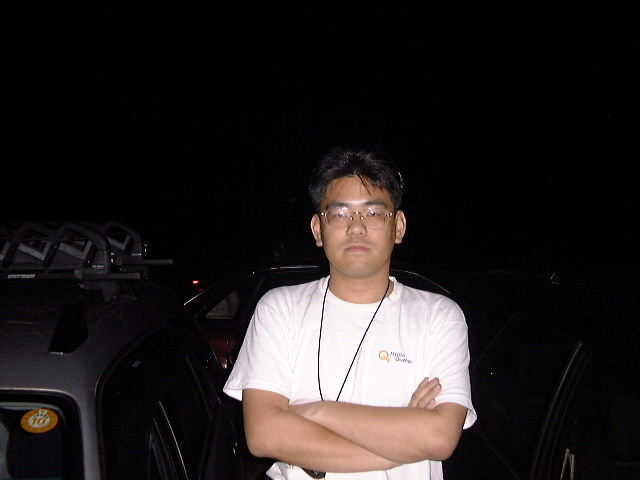

コメント