真っ正面の、平らな部分が「槍の肩」と呼ばれているところで、ここに槍岳山荘がある。収容人数も多く、槍ヶ岳に登る人の多くはここに泊まる。標高3060m、収容人数は650人。こんなところによくもまあ・・・と思うが、それでもハイシーズンだとおなじみの「寝場所確保合戦」が繰り広げられ、「1畳に人は何人寝ることができるか?」というギネスにも何にも認定されない不毛なバトルが展開されることになる。
ヒュッテ大槍はメイン登山道から外れている事もあり、ハイシーズンでも比較的楽に宿泊できる穴場だと聞いている。ならば、山頂に近いけど混んでいる山小屋よりはるかにいい。
しかも、燕山荘のオーナーが道楽でやっているという噂があり、「夕食にワインがサービスされる」とか「飯が山小屋にしては異様に良い」とか、しまいには「サラダバーがあった」などという話が出てくる始末。これは、行かないわけにはいくまい。ところで、サラダバーって本当か?うそだろ?
下の方から、さっきのガハハハ親父が相変わらず大きな声でしゃべりながら登っているのが聞こえる。呆れた、あのオッサン登っている最中もしゃべりを一切やめようとしないぞ。登山道の分岐点に親父がさしかかり、僕は「こっちくるな光線」を2割り増しで送りつけた結果そのまま直進してくれた。ほっと一安心。


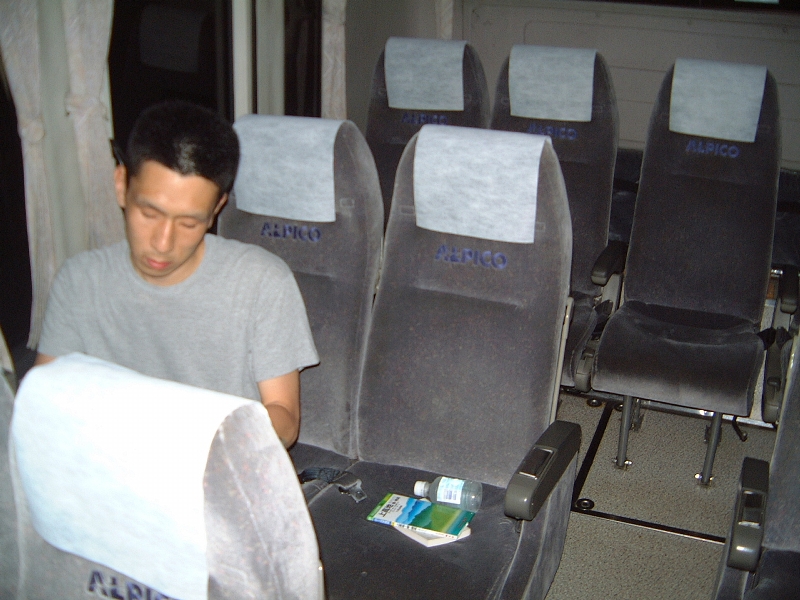



コメント