
14:15
小屋があるところから少しだけ甲州側に下ったところに、トイレが二棟ある。
甲州側だから甲州トイレだな、としょうもないことを思いついた。
どっちかが男性用でどっちかが女性用という区別はない。お好きな方をどうぞ。ちなみに全部個室。
これがうわさに聞く、農鳥小屋のトイレなのか。
小屋に先着していた登山客も、
「トイレはあらかじめ見ておいた方がいいよ。夜になって行くとびっくりするから」
と笑いながら言ってたっけ。

14:15
トイレの脇からトイレを見てみる。
あー。
もちろんバイオトイレなんて高度なものがあるわけではなく、いわゆる放流式だ。つまり、排せつ物はそのまま下に落ちる、と。
しかし、このトイレは絶壁の上に建っているわけではない。普通の斜面の上にある。
そういうこともあってか、トイレの下には、滑り台のように傾斜がついた「とい」が敷いてあった。
トイレで用を足すと、下に落ちたのちこの「とい」を伝って転がり落ちていくというわけだ。
排せつ物が白日の下にさらされているわけで、あまり気持ちの良いものではない。
しかも、このトイレがある先にテント場があるというのがシュールだ。テント場の人、臭いは問題ないのだろうか?
おじさんに言わせれば、「人間が生きていく上で当然排せつするだろ。自然の摂理だ、汚いとか隠せとか言うな」なんだろうな。

14:16
トイレの個室をのぞいてみる。
崖下方面におしりを向けて、穴に用をたすのだが・・・
ああ、いけませんいけません、穴から見える「とい」に、排せつ物がひっかかってるのが丸見えだ。
水洗式じゃないので、途中で止まってしまうんだな。
ああー。あんまり見たくないもの、見ちゃったよ。
こういう「生きていく上で当たり前」のものを隠蔽してきたのが、近代日本の建築であり、文化であり、技術なんだなと思う。

14:31
小屋に戻り、自分の寝床を確保してみる。
敷き布団や掛け布団といったものはない。あるのは、毛布と枕だけだ。
毛布を使って、自分の陣地を主張する。
一応、肩幅くらいのスペースは確保することができた。上でき。
敷き布団だと、天日干しにするのが重労働になる。だから、軽いし取り回しが楽な毛布を採用しているのだろう。合理的だ。寝泊まりする側だって、湿気を吸ってしっとりした敷き布団なんかより、毛布の方がよっぽどましだ。
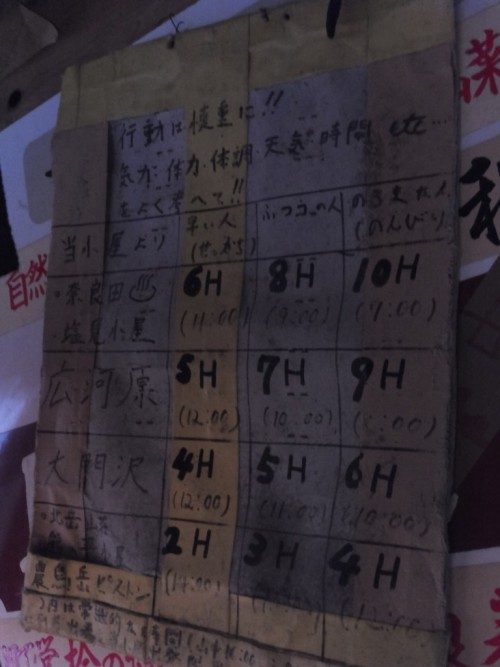
14:32
枕元に、こんな張り紙があった。
ここから各方面に向かう際の所要時間をまとめたものだ。おじさん、親切だ。
ただし、書いてある内容はおじさん風である。
たとえば、おかでんが明日のゴール地点と据えている奈良田温泉だが、
「早い人(せっかち) 6h」「ふつうの人 8h」「のろまな人(のんびり) 10h」
と記されていた。
「のろま」という言葉をチョイスするあたりが、おじさん素敵。
奈良田温泉まで、8時間。結構な長丁場だ。奈良田に下山したからといって、すぐに帰京できるわけではない。ここもまたとんでもない秘境で、一日4本しかないバスを捕まえて、身延線の駅まで行って、そこから甲府に出て・・・とやらないと帰れない。
明日は最終日だからといって、気が抜けないのだった。長い下山ルート、気を許すとけがの元だ。

コメント